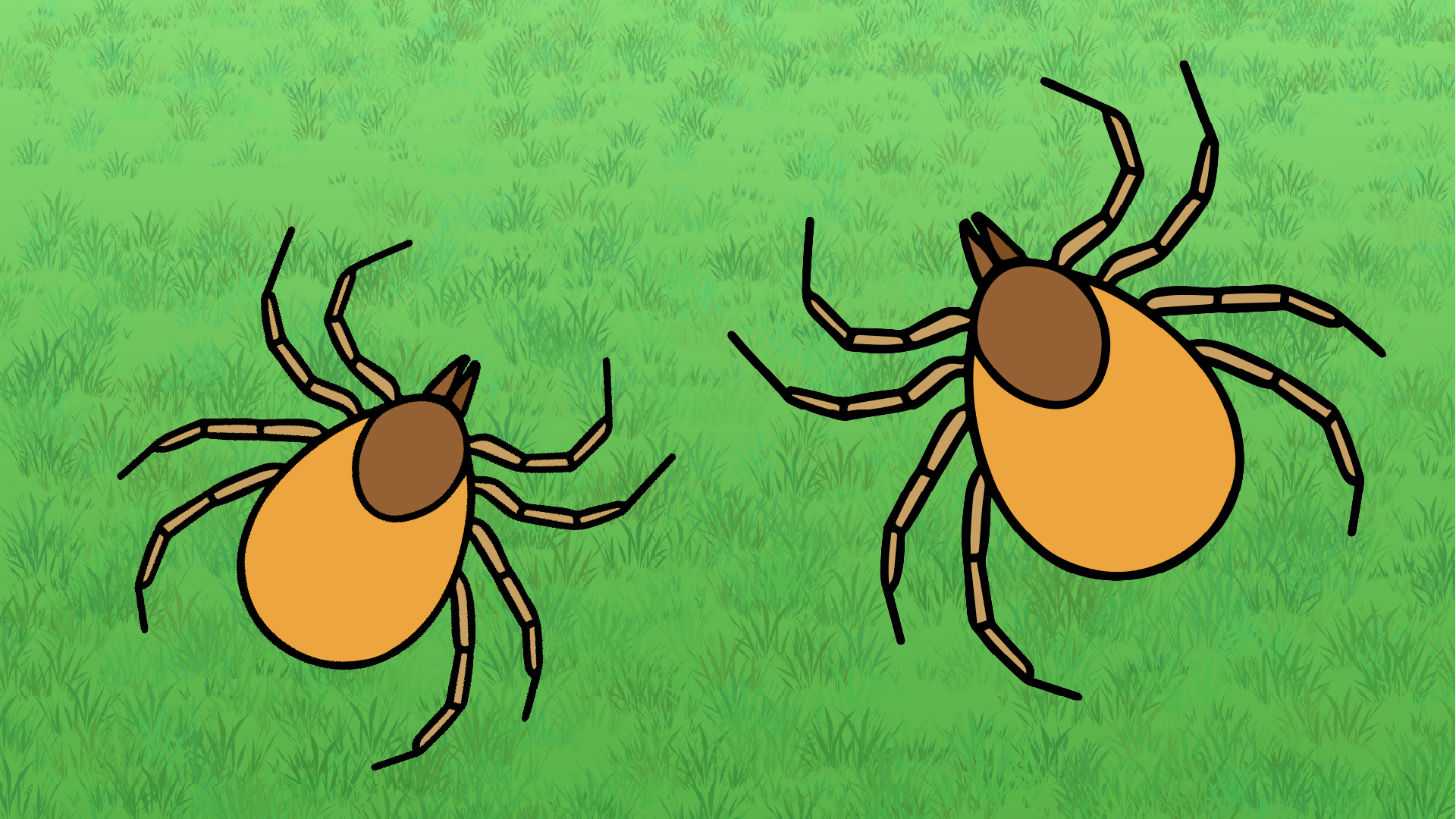最近、お亡くなりになった方がいらっしゃった事もあり、SFTS(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndromeー重症熱性血小板減少症候群)という感染症が注目を集めています。これは、マダニに咬まれることで感染するウイルス性疾患で、国内でも毎年重症化・死亡例が報告されています。
キャンプブームもあり、「自然の中でのびのび過ごしたい」「ペットと草むらを散歩したい」…そんな季節にこそ、マダニ対策が必要です。本記事では、SFTSとはどのような感染症なのか、またその予防はどうしたら良いのかを解説したいと思います。
SFTSって何?
SFTSは、マダニに咬まれることで感染するウイルス性疾患で、2011年に中国で初めて報告され、その後日本でも報告が相次いでいます。国内で分離された SFTS ウイルス株は、中国で分離されるウイルス株と異なり、長期間日本国内の自然界に存在していたと考えられています。近年、マダニ - 野生動物によるウイルスの感染環が、ヒトの生活圏に拡大している可能性が指摘されています。
SFTSは、中国、韓国、日本を含むアジア地域に分布するマダニ媒介性ウイルス性出血熱に分類されています。動物由来であることや致死率が高いこと、重症例では出血症状が認められること、患者や発症動物の血液・体液に接触した者が感染することなどの特徴があります。
SFTSのウィルスとその感染経路は?
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の病原体であるウイルスは、フェヌイウイルス科バンダウイルス属に分類されます。エンベロープを有し、ゲノムは3分節構造のマイナス鎖一本鎖 RNA で、単一の血清型を有すると考えられています。形質芽球に分化傾向を示すBリンパ球に感染します。感染症法においては、三種病原体に指定され、四類感染症に分類されています。
*エンベロープとは、ウィルス粒子を覆っている脂質二重膜のことです。それを持つウイルスはアルコール製剤が効きやすい性質があります。
主にマダニ(フタトゲチマダニ、タカサゴキララマダニ、キダチマダニなど)に咬まれることにより、感染します。感染者の血液や体液との直接接触でも感染することがあり、スタンダードプリコーションが必要な感染症です。ペットから感染した方や医療従事者の職業感染が報告されています。
感染したらどんな症状が出るの?
SFTS の潜伏期間は、6 〜14日間です。発熱、倦怠感、頭痛などの症状で発症することが多いです。また、嘔吐、下痢、腹痛などの消化器症状が認められることが多いです。リンパ節腫大や肝脾腫が起こる場合もあります。
血液検査では、白血球減少や血小板減少、トランスアミナーゼ高値が認められることが多いです。また、尿検査ではほとんどの患者さんで血尿が見られます。重症化すると急性脳症や急性腎不全、心機能障害などが起こり死亡する場合もあります。
マダニの吸血メカニズム
マダニは吸血性の節足動物です。マダニの栄養源は、宿主の血液のみで吸血できないと発育や繁殖ができません。マダニが栄養を摂取する時期は、幼虫期、若虫期、成虫期にそれぞれ1回づつです(一生で3回だけです)。
多くのマダニは咬み、皮膚を切り裂いてから5~30分以内に、傷口に唾液の一種であるセメント物質を分泌します。このセメント物質は分泌後すぐに固まり、口の周囲をラテックスのように覆うことでマダニの付着を強固なものとします。その他、マダニの唾液には、止血阻害物質や抗免疫物質、血管新生や組織再構築の阻害物質などが含まれ、アレルギー反応を引き起こします。数日間緩慢に吸血した後、約24時間という短時間で急速かつ大量の吸血を行います。
マダニの吸血の特徴は、知溜まり(Blood Pool)を作ることです。このBlood Poolは、急速吸血期から観察されるようになり、特に満腹になる直前の24時間においては、口の直下に血溜まりを含む空洞様の変化が観察されます。そのため、吸血された時の組織破壊は大きいです。
感染予防対策は?
SFTSの感染予防策は、マダニに咬まれないことです。
マダニ類の被害はその活動期に発生するため、マダニの季節消長を把握することはマダニ媒介感染症対策の上でも重要です。季節消長が判明しているマダニ類は、大まかに2つのタイプがあります。春から秋にかけて活動するタイプと、秋から春にかけて活動するタイプです。一年中マダニは活動していると思っておくと良いです。また、寿命は数か月から数年と長く、不活発状態で生命を維持することができます。
マダニの生息地は、自然環境に広く分布しており草地や雑木林、森林の下草から都市部の公園や河川敷にも生息しています。したがって、マダニ対策は、マダニの生息地に行く事があれば、肌の露出を避け、もしマダニがついても見つけやすいように明るい色の服装を選ぶことが良いでしょう。また、ディートやイカリジンの入った虫よけスプレーが有効です。イカリジンは、お子様への安全性も確認されていますので、安心して使用できると思います。
もし、咬まれてしまった場合は、細いピンセットで皮膚を咬んでいる頭の部分(顎体部)を横から挟み、回転させながら引き抜くと除去できる可能性が高いです。ダニが皮膚に深く潜ってしまった場合は、皮膚科を受診して頂く方が良いと思います。マダニが媒介する病原体は、ウィルスだけでなく原虫や細菌もあります。感染予防対策をしっかり行って、レジャーを楽しんで頂きたいと思います。
参考文献
重症熱性血小板減少症候群 診療の手引き2024年版 厚生労働省
マダニの科学 白藤梨可・八田岳士・中尾 亮・島野智之編集 朝倉書店 2024年
感染症診療とダニワールド 企画 竹原 敬・葱那賢志 臨床医学eBOOK 2016年