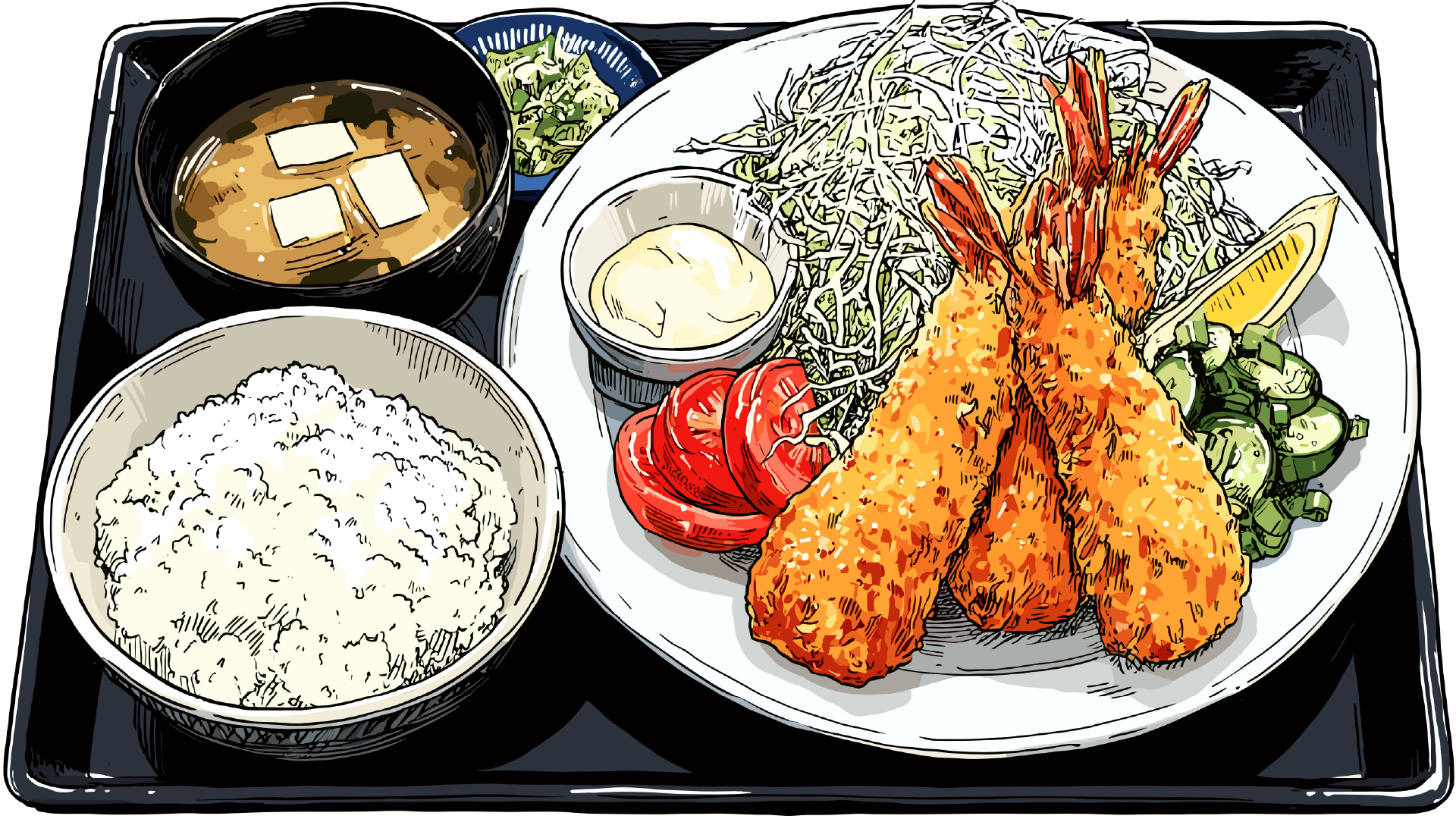2017年ノーベル生理学・医学賞に学ぶ「体内時計」のメカニズム
高齢者の食事時間が健康に影響する背景には、人の「体内時計(サーカディアンリズム)」の存在があります。この仕組みを解き明かしたのが、2017年にノーベル生理学・医学賞を受賞した ジェフリー・C・ホール、マイケル・ロスバッシュ、マイケル・W・ヤング の3名の博士です。
彼らはショウジョウバエを使い、体内時計を制御する「 period遺伝子 」を発見しました。
- period 遺伝子がつくる PERタンパク質は細胞内に蓄積すると核に戻り、自分の遺伝子の働きを抑制します。この「負のフィードバックループ」が約24時間周期で繰り返され、私たちの体内時計を刻みます。
- このメカニズムはtimeless (TIM)、doubletime (DBT) など他の遺伝子も加わり、外界の光や温度等に同調して、体のリズムを整えています。
現在では、様々な生物で時計遺伝子の存在が確認されています。生物の細胞には時計遺伝子が存在し、それらの細胞が相互に影響し合い体内時計は働き、身体を動かす「時間」を生み出すことが分かっています。現在では、睡眠やホルモン分泌、代謝などを調整する「時計遺伝子」の働きの研究が加速しています。今回は、国際的な医学ジャーナルのCommunications medicineに掲載された最新研究をご紹介したいと思います。
高齢者の「食事時間」と健康アウトカムをめぐる最新研究
英国在住の高齢者約3,000人を数十年にわたり追跡調査した結果、加齢とともに朝食と夕食が遅くなる傾向が確認され、加齢にともなう朝食時間の遅延は死亡リスクの上昇と関連しているとの研究結果でした。また、疲労、口腔健康問題、抑うつ、不安、多発性疾患を含む身体的・精神的疾患は、朝食が遅いことと関連している研究結果でした。
私たちは健康長寿であるために「何を食べるか」に注目しがちですが、この研究で「いつ食べるか(食事時間)」も健康や寿命に大きな影響があるということが分かりました。単に「何を食べるか」や「どれだけ食べるか」ではなく、「いつ食べるか」を重視する新しい栄養学に「時間栄養学」というものがあります。時間栄養学はとても面白いので、今後コラムでご紹介したいと思います。
「いつ食べるか」を訪問看護サービス価値にする
訪問看護では、服薬や栄養バランス指導だけでなく、「いつ食べるか」という時間栄養学の視点を取り入れることが可能です。高齢者の方は生活リズムが乱れやすく、遅い夕食や朝食欠食、間食の増加などの生活習慣が疾患リスクにつながります。訪問看護師は生活環境や服薬スケジュール、睡眠習慣を総合的に把握できる立場にあるため、時間栄養の指導は訪問看護ならではの付加価値となります。メティスでも今後、臨床栄養学に時間栄養学を取り入れた栄養指導の研修を検討したいと思います。
参考文献
Hassan S Dashti, Chloe Liu, Hao Deng, Anushka Sharma, Antony Payton, Asri Maharani, Altug Didikoglu. Meal timing trajectories in older adults and their associations with morbidity, genetic profiles, and mortality. Communications medicine. 2025 Sep 04;5(1);385. pii: 385.