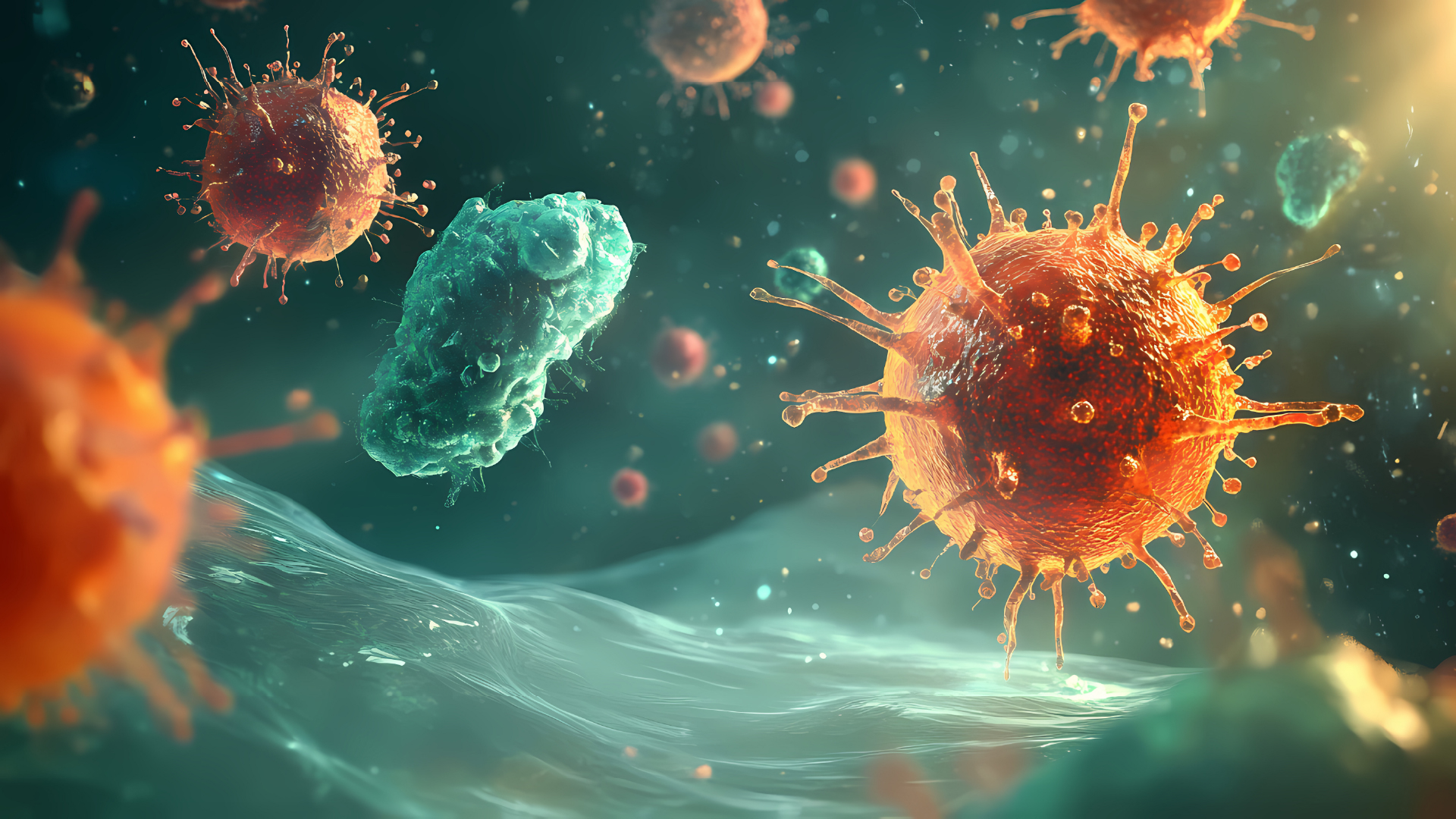私たちの体にそなわっている免疫システムは、ウイルスや細菌などの病原体や異物を徹底的に排除する一方で、自分自身の正常な細胞には無反応です。病原体や異物であっても、その時の状況によっては無反応のこともあります。この無反応な免疫状態を「免疫寛容immune tolerance」といい、とくに自分の細胞に対して無反応な状態を自己免疫寛容といっています。
2025年のノーベル生理学・医学賞は、この免疫寛容の中核を成す「制御性T細胞(regulatory T cells; Treg)」の発見とその制御機構に関する研究に対して授与されました。日本人では、大阪大学の坂口志文特任教授が授与されました!!おめでとうございます!!
そもそもの免疫応答の仕組み
免疫応答は、個体の恒常性維持機能のひとつです。免疫は「自然免疫」と「獲得免疫」に大別されます。生来備わっている「自然免疫」では、異物を貪食するマクロファージなどの細胞が中心となって働いています。一方、「獲得免疫」は、異物を認識して抗原特異的に応答するもので、T細胞やB細胞などのリンパ球が中心に働いています。
「獲得免疫」は、さらに「細胞性免疫」と「体液性免疫」があります。「細胞性免疫」は、主にT細胞が担う免疫の反応です。1型ヘルパーT細胞が抗原を認識すると、細胞傷害性T細胞(キラーT細胞)が活性化されて、病原体に感染した異常細胞を攻撃します。一方、「体液性免疫」は、B細胞が主役になります。2型ヘルパーT細胞の補助によって、B細胞が形質細胞(抗体産生細胞)へと分化して、B細胞から産生された大量の抗体が体液を介して全身に広がります。具体的には、1個のB細胞から1週間以内に5,000個もの抗体産生細胞が作られ、それぞれの抗体産生細胞から毎秒2,000個の抗体を分泌します。
白血球の中のリンパ球には、T細胞とB細胞があり、さらにT細胞はヘルパーT細胞、細胞傷害性T細胞、制御性T細胞などに分けられ、それぞれが特有な免疫応答を担っていることが明らかになっています。
制御性T細胞とは何か?
制御性T細胞(Treg;Tレグ)は、免疫反応を抑制的に制御するように働くリンパ球です。Tレグは、自己の細胞を攻撃しそうなT細胞も抑制します。
これにより、リウマチや1型糖尿病、潰瘍性大腸炎などの自己免疫疾患を防いでいます。
Tレグは、胸腺内で分化し自己抗原に特異的なtTreg(thymus-derived Treg)と、末梢組織で分化する自己抗原あるいは外来抗原に特異的なpTreg(peripherally-derived Treg)が存在します。
Tレグによる免疫抑制の仕組みは、実は1つではなく、複数の層で多段階的に免疫を抑制しています。1つは、TGF-β(トランスフォーミング成長因子β)やIL-10、IL-35などの炎症を鎮める分子(抑制性サイトカイン)を放出して、免疫の過剰反応を抑えます。また、他の免疫細胞に直接触れることで抑制シグナルを送る接触依存的な抑制も行っています。さらには、免疫細胞(特にT細胞)が増殖・活性化するためには、IL-2が必要です。TレグはこのIL-2を受け取るための受容体 CD25(IL-2Rα) を大量に発現して消費することで、他のT細胞の増殖・活性化を抑制します。そして、樹状細胞(抗原提示細胞)やB細胞の制御も行います。
臨床応用と将来展望
Tレグを用いた免疫療法が有望視されている分野は、がん、臓器移植の拒絶反応、自己免疫疾患、感染症、アレルギー疾患、生活習慣病と幅広い病気に及んでいます。それは、ステロイドのように免疫全般を抑制するようなものではなく、抗原に特異的に反応するリンパ球だけを抑制できるからです。たとえば、移植の際に問題となる拒絶反応は主にT細胞によるもので、ドナーのMHC分子を異物として認識するレシピエントのT細胞が移植片を攻撃するからで、このレシピエントのT細胞だけを抑制するTレグで処理する(補う)ことで拒絶が回避できることになります。がん細胞に対してはキラーT細胞がその排除を担うのですが、病巣におけるキラーT細胞に対するTレグの割合いが高い場合には、予後が不良とされています。したがって、腫瘍局所のTレグを減らすことが効果的と考えられます。
このように、Tレグを適度に補ったり、減らしたりすることによって免疫応答をコントロールすることで、いろいろな疾患を治せる可能性があることが期待されているのです。
参考文献
分子細胞免疫学 原著第10版 アバス・リックマン・ピレ
免疫の守護者 制御性T細胞とはなにか 坂口志文 篠崎朝子 講談社
免疫ペディア 熊ノ郷 淳 羊土社